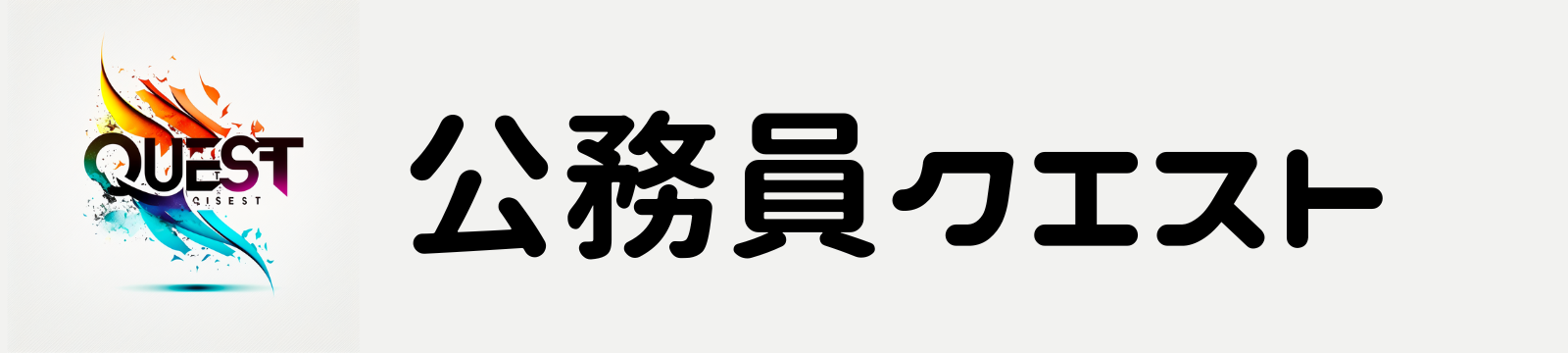退職の報告ってまず誰にすればよいのかしら?



家族がいると色々な手続きが必要そうだなあ
転職先から内定をもらい、ほっとするのも束の間。
次にすべきことは退職することを上司に伝え、辞める準備に取り掛かることです。
今までおこなっていた仕事の棚卸しをし、後任が苦労しないように引継書を作成したり、職場の人に仕事の進捗状況共有など自分しかわからないと思われることを引き継いでおく必要があります。
このタイミングでしっかりと引き継ぎができていないと、退職後にも連絡がきて、新しい職場の仕事にも支障が出るので丁寧な引き継ぎを心がけましょう。
「立つ鳥跡を濁さず」ということわざもあるように、これまでお世話になった職場に恩を仇で返すことにならないよう、最後まで気を抜かないようにしましょう。
この記事では夫の転職先が決まってから市役所を辞めるまでの激動の期間を振り返ります。
これから市役所を退職される方の参考になれば幸いです。
\この記事はこんな人におすすめ!/
- これから公務員を退職しようと思っている人
- 新しい道を歩み始めようとしている人
合格発表の後は大忙し


夫の転職先が決まったのは年が明けてからでした。
転職先の決定が遅かった影響により、転職決定から新しい職場に移るまで仕事はもちろん、プライベートでもかなり目まぐるしく、新生活から約半年経って、ようやくわが家のペースが取り戻せてきた感じです。
まずは、所属長(課長)に退職報告
まず最初に退職の報告したのは、所属長である課長でした。
少しでも早く報告をすることで来年度の組織体制に悪影響が出ないようにと思い、最終合格発表が出た翌日には報告をしました。
夫自身も報告する際はとても緊張したとのことでしたが、報告の際に意識していたことは下記のことです。
退職の相談ではなく、退職の報告
今の職場では、対処できない課題の設定
退職の相談ではなく、退職の報告
所属長への退職報告は『報告』であって、『相談』ではありません。
上司に退職するかどうか迷っていると相談すれば、大抵の上司は退職を阻止してきます。
その理由は人事評価において、部下の管理能力がないということでマイナス評価をつけられるからです。
なので、上司は少しでも残留の可能性があるのであれば、退職を考えている原因を取り払うから辞めないでほしいと説得してくるでしょう。
相談ではなく、退職する意思が固まったことの報告をするといった毅然とした態度で退職報告を上司に行いましょう。
今の職場では、対処できない課題の設定
退職する時には円満に退職をしたいと思う人が多いと思います。
退職をするということは何かしら今の職場に不満を感じているから辞める人が多いのも事実です。
そのような不満から退職するといった経緯があったとしても、退職報告時に不満なことのみを退職理由にするのは得策ではありません。
冷静になって、相手の身にもなってみましょう。
今の職場の風通しが悪いから辞めます。と直球で言われた上司の気持ちを考えてみると、良い気分がするでしょうか。
ここは大人になって、上司が踏み込めない理由を設定し、今の職場が悪いから退職するのではないということを最後の優しさとして添えることが円満退社への第一歩だと思います。
親の介護や子どもの進学など家庭の問題については最もらしい理由になり、上司としても介入しづらいので円満に退職したい場合には使ってみてもよいかもしれません。



ちなみに夫はこれらを実践して、全く引き止められず、拍子抜けしていました(笑)
とはいえ、上司に退職報告をするのがどうしてもできない、職場に行くことを考えるだけで体調が悪くなる人も中にはいるかもしれません。
そのような人は最終手段として、退職代行業者を使って退職することも一つの手です。
退職代行では出社しなくても、退職をすることが可能です。
最後の砦として、どうしても自分から退職報告ができない人は検討してみても良いでしょう。
同僚・同期への報告
同じ課内の同僚については、普段の業務から助け合って仕事をしている仲であり、退職することで一番影響を受けます。
そのようなことからも、退職報告のタイミングは大切です。
あまり早くに言い過ぎてしまうと、仕事がやりにくくなる一方で、遅すぎると引き継ぎがまともにできなくなります。
例えば、1ヶ月ほぼ決まったルーティンで仕事が組んであるものであれば、そのルーティンの時に合わせて、引き継ぎをすることもでき、気持ちに余裕も持ちやすいでしょう。



同期については部署も別々だし、LINEで報告でいいかもね
仕事の引き継ぎ
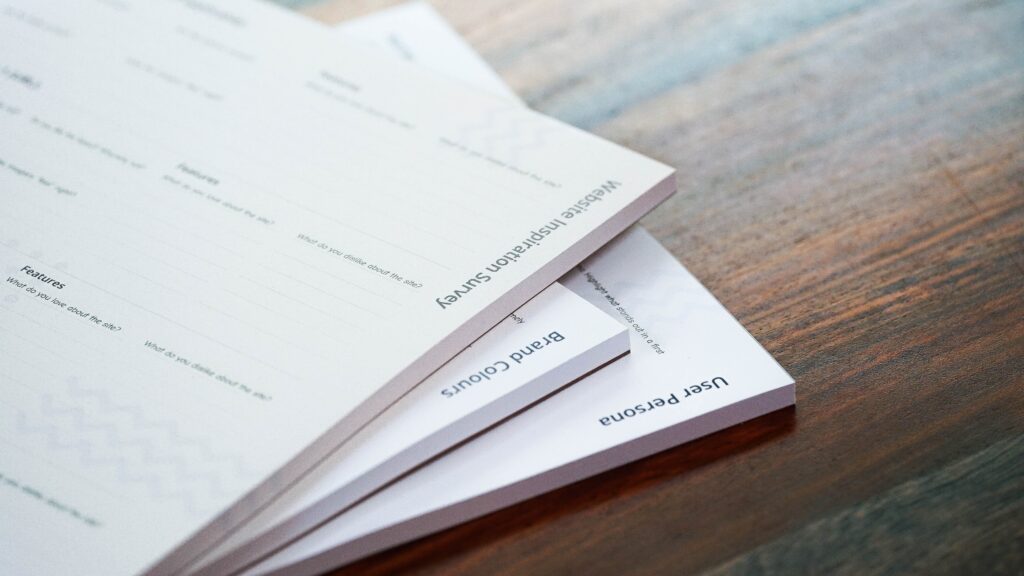
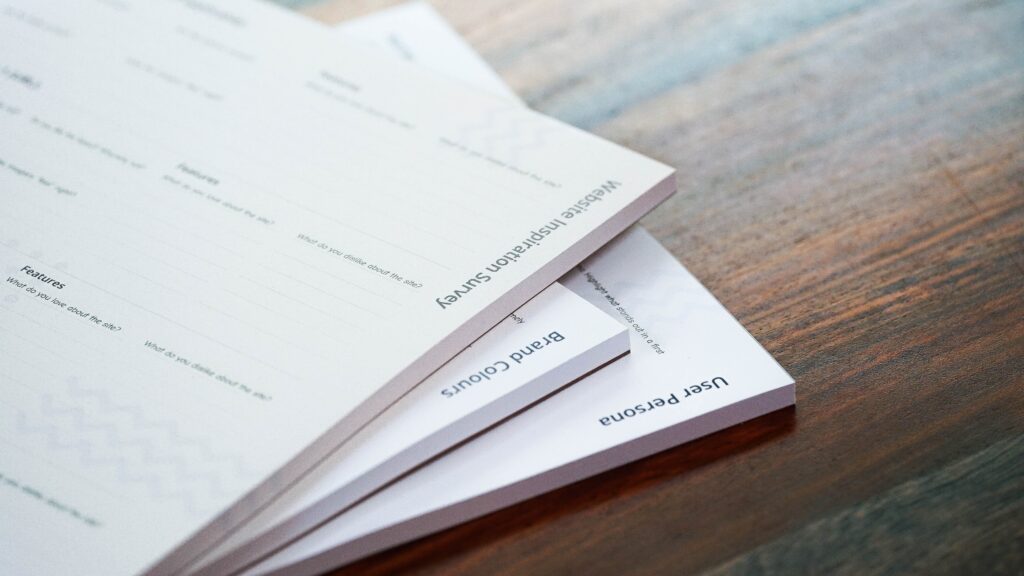
退職する際には、次の担当者が困らないように引継書を作成します。
部署異動の際にも、引継書を作成して後任者に業務を引き継ぎますが、異動の場合は引継書を見て理解できなければ、前担当者に内線で確認することもできます。
ただし、退職となると気軽に聞くことができません。
そのようなことからも異動の時に作成する引継書よりも丁寧に作成するように心がけましょう。
丁寧に引継書を作成することで、退職後に問い合わせが減りあなたの負担も少なくなります。
引継書の作成
公務員の仕事は後任者が困らないように引継書を作成して事務を引き渡します。
事務の一連の流れやイレギュラー時の対応など、事細かに記載することがポイントです。
システムに入力する事務は実際にスクリーンショットなどで画面コピーをした上で、時系列に沿って入力箇所を記載していくことで文字だけの場合よりもイメージもしやすくなります。
仕事の都合をつけられることができれば、有休消化も可能
有休消化することは労働者として認められています。
しかし、現実は有給を全て消化して退職するのは難しいと思います。
夫も3月の最後の1週間は引越があるため、有給を取ることができましたが、40日間全てを消化することはできませんでした。
一方で、中には40日全て消化して退職していった同僚がいたり、退職の最後の日まで残業をして有給を全く取得せずに退職したりするものもいたりしたので人それぞれなところが多いです。
有給取得をしたいのであれば、以下の点を普段から意識しておく必要があります。
同じ課の人との良好な人間関係を築いておく
仕事について、自分にしかわからないものを極力減らし、情報共有しておく
良好な人間関係を築いておくと、仕事もやりやすくなり、退職時にも気持ちよく送ってもらうことができます。
仕事のちょっとした隙間に何気ないプライベートな話をすることで、距離が縮まったりするので積極的に話をしてみると良いでしょう。
仕事について、公務員の仕事は属人化しやすいです。
担当が厳密に分かれており、進捗をその都度記録に残したりすることがないため、担当が休んだ場合は何もわからないといった状況が生じます。
そのような状況では、引継も大変なので、日頃から自分がいなくても対応できるように仕組みを作っておくこともポイントです。
プライベートの整理


転職先が決まった後、プライベートでも決めなければいけないことが増え、慌ただしくなります。
わが家の場合は、転居を伴うかつ未就学児がいたので、新居の内見や保育園見学などすき間の時間を使ってこなしました。
新居を探す(引越しが伴う場合)
わが家は住んていた家から新しい職場へ通勤することはできない距離だったので、引越し一択でした。
ただし、時間がない中での新居探し、土地勘がなかったこともあり、良い家をなかなか見つけることができませんでした。
転職が決まっていない段階で家を見にいくということは精神的にも難しいと思いますが、長い時間過ごす家なのでできるだけ時間をかけて見ることをおすすめします。
ちなみに、時間をかけられなかったわが家は新居選びに失敗し、半年後にはまた引越しをしてマイホームを購入しました。
マイホームを購入した時の記事は下のものなので、マイホーム購入を検討している人は参考にご覧ください。


新しい保育園を探す(子どもが未就学児の場合)
保育園は原則住んでいる自治体にある園に通うことになっており、市町村をまたいで引越しをする場合は転園する必要があります。
わが家の場合は、市町村をまたいでの引越しだったので保育園探しも同時に行いました。
ネットで口コミを調べて、実際に園の見学をして申し込みをしました。
ただし、申し込み時期が遅かったこともあり、二人の息子は別々の保育園に通うことになり、朝は同じ園に通ってくれていた時よりも準備や送迎が大変になっています。
もう少し早い段階で申し込みを行なっていれば、同じ園に通えたかもしれませんが、まだ転職先が決まっていない段階で入園申し込みすることは現実的には難しく、致し方ない結果です。
市役所やカード情報の登録関係を変更する
引越しをすると、市役所での住所変更が必要です。
わが家の場合、少しでも時間の節約をするため、ネットで行えることはネットで行いました。
前に住んでいた自治体では、転出届はマイナンバーカードを使ってオンラインで自宅からできたので行く手間が省くことができました。



マイナンバーカードって活用できて意外と便利ね
一方、転入届については市役所に行く必要がありました。
3月だったこともあり、住所変更するだけで何時間も待たされ、子どもは待ちきれず市役所内を走り回る始末。
子育て世帯には自宅からオンラインで好きな時に手続きできることがどれだけありがたいかを実感しました。
まとめ
今回は実際に市役所を退職した夫の経験に基づいた記事を書きました。
ポイントは
普段の仕事だけでも、やるべきことは無数にありますが最後の仕事と思って、『終わりよければ全て良し』の精神で良い締めくくりで職場を去りましょう!